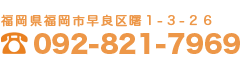保育内容について
保育内容について-
保育所保育指針に沿って、子どもたちの健やかで円満な人格形成の基礎づくりとして、情操の涵養、社会性・創造性の育成、身体の正常な発育の促進を目標としています。年令段階によりクラス編成し、その時期の心身発達のために5領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)について、子どもの人権を尊重し、ひとりひとりに視点をあてて保育を行います。また、基本的生活習慣の獲得と人間として豊かな情緒の発達の芽生えを育むことに重点をおいて保育しています。
 体育
体育
- 0才児から、体を動かすことの楽しさを体験できるよう運動あそびの時間を設けています。マット、トンネル、ルールあそびなど年齢に応じた様々な活動を行っています。3・4・5才児は、朝、体操やマラソンを行い、基礎体力作りを行います。また、夏季には、2・3才児は、屋上で水遊び、4・5才児は、屋上プールでプール活動を行います。運動習慣の基盤づくりを通して、幼児期に必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力を培うとともに、様々な活動への意欲や社会性、創造性などを育むことを目指します。
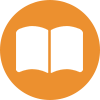 知育
知育
- 0才児から、聴覚・視覚を刺激し、年齢に応じた、絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。手や指を使った積み木やブロック・パズルあそびなどでは、観察力・想像力・集中力・記憶力を養います。3才児から、言葉や数字を使った知育が始まり、かく力、ことばを使う力、考える力の基礎を養います。5才児から音読を行い、保育士が一行ずつ読むのを聞いて、まねをすることから始め、日本語の響きの美しさを味わいます。5才児は、ひらがなの練習を行い、その集大成として、卒園文集を制作します。
 音楽教育
音楽教育
- 0才児から「良い耳」を育てることに努め、3才児から鍵盤ハーモニカのさぐり弾きを始めます。5才児は、本格的音楽の美しい旋律等を体験し、音楽性を高め、情緒の発達から情操への育成をめざし、毎年1月に福岡サンパレスで行われる器楽合奏の発表会(たんぽぽ音楽研究会発表会)に参加します。令和6年度は、『喜歌劇「軽騎兵」序曲』F.スッペ作曲、小沼和夫 編曲 を演奏しました。
また、歌をうたう活動や音楽に合わせて身体を動かすリトミックも保育の中に取り入れています。歌うことやリトミックは、感性を育て、記憶力の向上・リラックス効果など様々な面で子どもたちに良い影響を与えてくれます。
 造形活動
造形活動
- 一年を通して、子どもたちは、年齢ごとに考え、試し、想像しながら、多くの素材を使って造形活動を行います。0・1・2才児は、自分の手を使っての手型、未熟な線描きからなぐり描き、画面いっぱいにフィンガーペインティングを繰り広げ、描く作業が月齢、年齢につれて巧みに変化していきます。3・4才児は、友だちと目標に向かって話し合い、共同制作にも取り組みます。5才児は心身の発達が著しく、日頃の園生活での経験をもとに、意見を交換しながらテーマを決め、「素材を生かして工夫し、考え、共感したものを創造へ」と向かっていきます。 3・4・5才児は、絵画コンクールにも出品します。
- 専門講師による指導
| 体育指導 | 週1回(対象3才児・4才児・5才児) 全身機能を使って活動します。鉄棒、縄跳び、体操などを通して、体力作りを行います。 |
|---|---|
| 英会話指導 | 週1回(対象3才児・4才児・5才児) 日本語と異なる言葉を知り、英会話を楽しみます。 |
| 硬筆指導 | 月2回 (対象5才児) 書く時の姿勢、えんぴつの持ち方、書き順、字の形に気をつけながらひらがなの練習を行います。 |
| 音楽指導 | 年6回程度(対象5才児) 器楽合奏の発表会に向けて、実践的な指導を受けます。 |
- 課外教室(希望者のみ)
午後の時間を利用して、希望者は課外教室を受講できます。
西新保育園こすもすは会場の都合上、3才児からの受講となります。
| ゼンオン 音楽教室 | 対象2才児から高校生まで(幼児科・ピアノ科) 音楽の基礎的感覚をのばしながら、楽器の演奏能力を高めます。 |
|---|---|
| あおぞら 体育教室 | 対象2才児から小学6年生まで 幼児期から低学年に最も必要な運動の調整力を高めます。 |
| あおぞら サッカークラブ | 対象2才児から5才児まで 無理なく楽しく技術習得を目指し、運動の調整力を高めます。 |
| あおぞら 水泳クラブ | 対象5才児 泳力の向上はもちろん、安全に楽しく水に親しむことをめざします。 |
| プローグレス 英会話教室 | 対象2才児~小学6年生まで 外国人との自然なコミュニケーション力をつけながら、リスニング、発音、スピーキングの力をつけます。 |
- ◎クラス編成
- 年齢別のクラス編成を基本として保育実践をしますが、異年齢のつながりによる、よりよい心身の発達を願って、縦割り、混合保育を必要に応じて実践します。
- ◎5才児ゆり組〜1才児ちゅうりっぷ組は2グループで構成されていてグループでの活動も行います。
- 5才児…ゆり組
- 4才児…ひまわり組
- 3才児…ばら組
- 2才児…もも組
- 1才児…ちゅうりっぷ組
- 0才児…たんぽぽ組
 保護者の声
保護者の声- 令和3年度・平成28年度 卒園児保護者

- 令和3年度・令和元年度 卒園児保護者

0歳、西新保育園のたんぽぽ組に入園した時、初日から先生方に名前を呼んでいただき、もう名前を覚えてくださったんだと驚きました。哺乳瓶の飲み口や瓶をいくら変えてもなかなかミルクを飲めなかった娘でしたが、「レンゲで上手に飲めました。明日からコップで飲めます」と教えていただいた日には、子どものために工夫してくださったことが嬉しく、私はプロの先生方に子どもを育んでいただいているのだなと実感いたしました。また、長男が11年前に入園した頃は、どう「お母さん」になればいいのか不安で、行事のたびに園長先生のお話を食い入るように聞いていたことを思い出します。
新型コロナウイルスの影響が長引き、子どもたちが十分に園生活や行事を楽しめるのだろうかと思うこともありましたが、会場の規模や観客の数に関わらず、行事ごとに真剣に練習し、本番を迎える子どもたちの、日々の表情の変化を見るにつれ、それは杞憂に過ぎませんでした。特にゆり組での行事は大きな思い出です。10月の『運動会』でのかけっこ、体操、マーチング、11月の『生活発表会』でのえんとつ町のプエルのダンス、1月の『たんぽぽ音楽研究会発表会』でのスケーターワルツの合奏。どの行事も子どもたちは、一生懸命に練習し、ドキドキしながらリハーサルを乗り越え、本番で全力を出し切りました。行事のあと、靴箱のところで、我先にと、お父さんお母さんに自分ががんばったことを伝え、メダルを首にかけたまま帰る姿を今でもはっきりと覚えています。
保護者が知っている、保育園での子どもの様子はほんの一部でしょう。しかし、送迎の折にお友達と話す様子や、家での会話から、充実した園生活を行っていることを毎日感じていました。園長先生、そして先生方、私たちが保育できない時間に、子どもたちの心と精神と知恵を育んでくださり、ありがとうございました。また、私たち保護者にも成長する機会をいただき、ありがとうございました。この優しいたまご色の園舎にもう通わないと思うと、寂しくてたまりません。しかし、今、子どもたちは4月の小学校入学に向け、夢を膨らませ希望に満ちた表情をしています。西新保育園でのたくさんの思い出と、先生方にいただいた愛情を胸に、子どもたちは西新保育園を卒園いたします。最後になりますが、園長先生、先生方、すべての方々に心よりお礼申し上げます。
思い起こせば八年前、初めての保育園で、親から離れ、泣き出す長男をたんぽぽ組に預けた日のことを思い出します。初めての運動会、西新小学校の広いグラウンドで、各クラスのかけっこやゆり組さんのマーチングを見て、我が子のこれからの成長を想像し、最年長児までの道のりを大変先長く感じた事を鮮明に覚えています。その後、次男が生まれ、私は二児の母となり、八年間通い続けた保育園も、あっという間、淋しい気持ちでたまりません。
西新保育園ではたくさんの行事がありました。季節を感じる行事だけでなく、クラス皆で練習に取り組む運動会や生活発表会があり、先日のたんぽぽ音楽発表会では、がんばった達成感とたくさん褒められたうれしさで、頂いたメダルを胸に、なんとも誇らしげな我が子の表情が印象的でした。日々新たな経験を積み、多くのことを学んで成長していることを感じます。と同時に、行事に取り組む先生方の熱意や細やかな準備に、親として本当に頭が下がる思いでした。二年前からの新型コロナウィルスの感染拡大で、私達の生活すべてが一変しております。日々の保育活動も行事も感染対策が必要となり、この二年間の保育の現場での苦悩、ご苦労を思うと胸が痛みます。マスク・手洗い・手指消毒など、子どもたち自身も大切なことを理解し、十分頑張ってきたと思います。しかし現在の第六波では小さな子供たちへの感染も増え、自宅療養や登園自粛を余儀なくされることも珍しくなくなりました。先行きが見通せず不安な毎日ですが、園の中は、いつもと変わらず、子どもたちや先生方の明るい笑顔や声で満ち溢れていて、夕方お迎えに行くときはいつも気持ちが和んでおります。子どもたちが安心して保育園生活を送れるよう、職員皆様の日々のご尽力に感謝の気持ちでいっぱいです。
今では保育園の黄色い通園鞄が小さく背負いづらく感じるほど、体も大きくなった子供達ですが、今度は一回り大きなランドセルを背負って、四月からそれぞれ新たな場所で小学校生活を迎えます。長く過ごした西新保育園で、折々に園長先生から頂いた 涙あふれる温かいお言葉は、楽しい思い出やお友達との絆とともに、子供たちの心に染み込んでいると思います。他人を思いやる強く優しい心を持って、子どもたちはさらに成長し、これからの日本の未来を担ってくれることでしょう。私達保護者は、この西新保育園の素晴らしい先生方に子供達を大切に指導頂いた御恩を忘れません。
 給食について
給食について-
西新保育園では、栄養バランスのとれた献立を栄養士が作成し、子ども達の成長を助ける給食を提供しています。
献立には自然に近い低農薬による緑黄色野菜を始め、肉、魚をバランスよく取り入れています。また、旬の食材を取り入れることで、旬の食材が持つ栄養素を十分に摂取し、食事の中で四季を感じることができるよう努めています。また、3時のおやつの時間は、手作りのおやつや旬の果物を積極的に取り入れ、子どもたちにとって「楽しい時間」となっています。
健全な食生活は健康で豊かな人間性の基礎をなすものです。そこで、全年齢を対象に食育指導を行っています。本物の食材に触れる野菜の栽培(土作りから収穫まで)、パネルを用いた野菜・果物クイズなどを行い、日々の食生活に必要な知識や判断力を育成することはもとより、食を大切にし、楽しむ心を育んでいます。0・1・2才児クラスでは栄養士・調理員が給食時間に、子ども達にスプーンやはしの正しい持ち方やしっかり噛んで食べることの大切さも教えています。離乳食(初期・中期・後期)についてもご家庭と連携を取りながらお子さんに合わせて進めています。
食物アレルギーのお子さんには、医師の診断書に基づいて、アレルギー除去食の提供を行っています。食器を色で分け、複数人での確認を行い、給食室と保育室が連携をしっかりとって進めています。アレルギーの食事では、牛乳の代わりに豆乳を使用したり、小麦粉の代わりに米粉を使用したりと、味、見た目ともになるべく普通食に近づけるよう心掛けています。

- 午前 牛乳 おやつ1回
- 昼食 主食 副食
- 午後 飲み物 おやつ1回

- 昼食 副食(主食は家庭持参)
- 午後 飲み物 おやつ1回
- ◎延長保育の子どもたちには、おやつを提供します。
 開園時間について
開園時間について

- 7時00分 ~ 18時00分(延長保育 19時00分まで)
-
(保育短時間の方の保育時間は8時30分~16時30分です。)

- (1時間延長)月~土 18時00分~19時00分
- 希望者は、所定の様式で保育園に申し込みください。
休園日
日曜日、祝日、国民の休日
年末年始(12月29日~1月3日)
- ※原則として、仕事が早く終わられた時は早く迎え子どもとのコミュニケーションふれあいを大切にしてください。
- ※お迎えが遅れる時は、必ず事前にご連絡をお願いしています。公平性を保つために、時間を超過した場合は、
超過時間に関わらず、延長料金をいただいています。
 保育園での衛生管理について
保育園での衛生管理について-
保育園では、次のような衛生対策に取り組んでいます。
-
○泡ハンドソープによる手洗い、うがい
(お子さんが使用する手洗い場の水栓は、自動水栓もしくはワンプッシュ水栓を採用しています。) -
○健康観察(朝夕の検温含む)
日々の検温では、非接触体温計を使用し、非接触体温計で平熱より体温が高い場合やいつもと様子が違う場合は、消毒した接触体温計で測定しています。 -
○毎日の園舎清掃及び消毒(消毒は、人が触れる部分を中心に行います。)
-
○おもちゃ類の消毒
-
○保育室に空気清浄機や加湿器、温度計・湿度計・二酸化炭素濃度測定器、サーキュレーターを完備し、窓を開け、園舎内の換気を行います。
※雨が降りこむ場合は、窓を閉めることがあります。
※寒い日は、二酸化炭素濃度測定器を参考にしながら、30分ごとに5分間を目安に窓を開け換気を行います。



 西新保育園(にしじんほいくえん)
西新保育園(にしじんほいくえん)
 くわしくはこちら
くわしくはこちら